教育デジタル化の縁の下の力持ち、その名は・・・
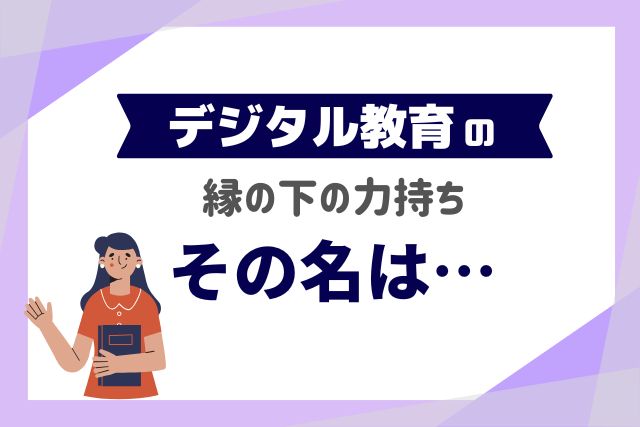
教育現場のデジタル化とICT支援員の不足
近年、教育現場におけるデジタル化が急速に進んでおり、小中学校の子どもたちにも学習用タブレットが一人一台ずつ配備されています。
このデジタル化を支える縁の下の力持ちが「ICT支援員」です。
ICT支援員は、先生や子どもたちがICT(情報通信技術)で困っているときに助けてくれる、非常に頼りになる存在です。
文部科学省は、2022年までに4校に1名のICT支援員を配置する目標を設定していましたが、実際には15校に1名程度の配置に留まっており、2022年度末時点では約8,500名が不足していると報告されています。
2024年末時点でも、ICT支援員の配置は依然として目標に達しておらず、多くの学校で支援が不足している状況です。
デジタル化が生徒の学習意欲と成果に与える影響
デジタル化が進む教育現場で、生徒たちの学習意欲や成果にどのような変化が見られるのでしょうか。
文部科学省によると、デジタル教科書の導入により、生徒たちの学習意欲が向上したという報告があります。
2020年度の調査では、デジタル教科書を使用した授業では、生徒の約60%が「興味や関心を持てる授業だった」と回答しており、紙の教科書を使用した授業よりも高い割合を示しています。
また、学習成果に関してもポジティブな変化が見られています。
例えば、デジタル教科書を使用した授業では、生徒たちが主体的に学ぶ姿勢が強化され、対話的な学びが促進される傾向があることがわかりました。
デジタル教科書を使用した授業では、生徒たちが自分の考えを他の人に説明する活動が増え、学びの深さが向上したとされています。
さらに、特別な配慮を必要とする生徒にとっても、デジタル化は大きな助けとなっています。
例えば、視覚障害を持つ生徒がデジタル教科書を使用することで、文字の拡大や音声読み上げ機能を活用し、学習の困難を軽減することができるようになったと報告されています。
ICT支援員の重要性と役割
これらのデータから、教育のデジタル化が生徒たちの学習意欲や成果に与えるポジティブな影響が表れています。
今後もデジタル化の進展に伴い、さらに多くの生徒がその恩恵を受けることが期待できます。
そのため、デジタル教科書の普及に伴い、ICT支援員の重要性がますます高まっています。
ICT支援員になるためには、公的な資格取得の必要はありませんが、「教育情報化コーディネータ検定試験」や「ICT支援員能力認定試験」という試験があり、ICT支援員の派遣事業者では、全ICT支援員にこの認定取得を義務付けているところもあります。
弊社のICT支援員も認定証を取得しています。
ICT支援員を目指す方は、これらの認定証の取得がおすすめです。
ICT支援員の主な役割を簡潔に説明すると、
1.パソコンやタブレットなどがトラブルに巻き込まれた際の技術サポート
2.ICTを活用した授業計画や実施方法を先生にアドバイスする教育サポート
3.ICT機器の使い方を教え、先生のスキル向上をサポート
などが挙げられます。
パソコンやタブレットの基本操作からトラブルシューティングまで幅広い知識が必要となるほか、教育現場でのICT活用方法や教育理論についての理解を深めることが大切です。
また、先生や子どもたちとの円滑なコミュニケーションを取る力もとても重要になります。
ICT支援員としてのキャリアスタート
ICT支援員としてのキャリアをスタートするには、教育委員会や学校、ICT関連企業などから求人情報が出ているのでチェックしてみてください。
地方ではICT支援員の人数が限られているため、都市部での経験を積むことも一つの方法です。
ICT支援員はデジタル教育が進むにつれて、ますます需要が増える職業です。
人を育てる教育の一部に携われることは、やりがいもあり、魅力的な仕事です。教育のデジタル化を支えるために、あなたも教育デジタル化の縁の下の力持ち「ICT支援員」になってみませんか?
出典:文部科学省ホームページ(https://www.mext.go.jp/)



